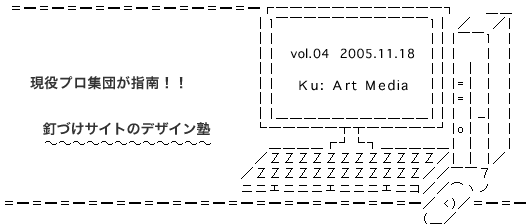| 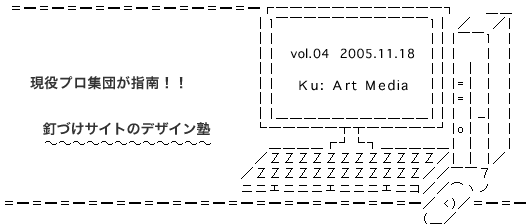
━ CONTENTS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ イントロダクション ----------------- 磨くのは、あなた=商品力=情報力
★ デザイン --------【ホームページデザイン前にすること(4) ラフスケッチ】
★ コピーライティング -----------------【「新聞の見出し」に見る誘惑テク】
★ 写真撮影・画像処理 ------------------【デジタルカメラ撮影術〜基礎編】
★ プランニング --【続・ネットで成功するための、『システムとノウハウ』】
☆ インフォメーション ----------- 当メルマガの活用法&塾生(購読者)特典
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ イントロダクション ----------------------------------- 当メルマガの目的
広告界を例に見ると、
よい商品は、たいてい、優れた広告を生み出しています。
ウォークマン、スーパードライ、かつての西武百貨店、
最近では、i-Podなど。
いい商品は、何もしないでも売れる。
これは、嘘です。結果論です。
コミュニケーションがうまくいかなかったせいで、
埋もれていった商品は幾らでもあります。
皆さんは「三木聖子」という70年代のアイドル歌手をご存知ですか?
テレビにもよく出ていて、
それなりにメディアに露出していたのに、売れなかった。
ちょうどピンクレディなんかの時期の人です。
彼女は、後に「石川ひとみ」でヒットした、
荒井由美作詞作曲の『まちぶせ』という歌を最初に歌った人なのです。
残念ながら、いい歌だったのに売れなかった。
荒井由美のネームバリューもいまほどではない時代でもありました。
しかし、時が過ぎ、荒井由実は、松任谷由美に変わり、
彼女のディスコグラフィに関心や知識を持つ人々も多くなった時期に、
『まちぶせ』は再リリースされました。
もともとあった商品力は、ファンの間で、
不遇だった過去の名作として自然と磨かれ、高まっていました。
情報力も、松任谷由美を知る年齢層の拡大により
普遍化される力を蓄えられていました。
結果は、皆さん、ご存知ですよね。
石川ひとみを代表する大ヒット曲に。
わたしたちは、
あなたをネットビジネスにおける「三木聖子」さんのような存在に
したくはないのです。
さあ、今回も、あなたのサイトを、
大ヒットサイトに変えるための講義をはじめましょう!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・◇ 倉田 浩孝 KURATA HIROTAKA
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━ HPデザイン前にすること(4)
┃
┃ ラ フ ス ケ ッ チ = 設 計 図 を し っ か り 固 め よ う
┃
┃
┃ みなさん こんにちは!
┃
┃ 回を重ねるごとに人数が増えてきているそうで
┃
┃ うれしいと同時に気が引き締まる思いです。
┃
┃ 私たちも頑張っていきますので これからもどうぞよろしくお願いいたします。
┃
┃
┃
┃ では、今日もさっそくはじめましょう。
┃
┃
┃
┃ 「広告づくりのノウハウをホームページ造りにも生かしていこう!」
┃
┃ ということでスタートしましたが、
┃
┃
┃
┃ 「デザインって、まだ何もしていないじゃん!」
┃
┃
┃
┃ いえいえ、もうどっぷり入り込んでいるのですよ、実は。
┃
┃
┃
┃ デザインをする前に《すること》が、いちばん大事なんです。
┃
┃ いわば基本中の基本。そして、基本は普遍です。
┃
┃ 構想をまとめること、考えること・・・いかがですか?
┃
┃ 既にデザインは始まっているんです!
┃
┃
┃
┃ 上辺だけのテクニックで前にばかり進もうとするとあとで結果が出なくて
┃
┃ 「な〜んだ」とがっかりすることになってしまうんです。
┃
┃
┃
┃ 前回、1枚に1項目ずつ書いたたくさんのメモ。
┃
┃ バラバラの紙を各項目を整理して並べていきました。
┃
┃ そして《ラフスケッチ》を描いていただきましたね。
┃
┃ 皆さんはお気づきのことと思いますが,
┃
┃ 紙を並べるときに伝えたい内容により順番を考えたでしょう?
┃
┃
┃
┃ 内容を分類し,整理して,どう見せていくかを考える・・・、
┃
┃ そう、このことがもうデザインをしていることなのです。
┃
┃
┃
┃ ・伝えたい情報(商品・サービス・イベントなど)をどう伝えるのかを考える
┃
┃ ・ホームページのタイトルを考える
┃
┃ ・1ページ目(トップページ)の内容を考える
┃
┃ ・2ページ目以降をどう組み合わせてわかりやすく案内するかを考える
┃
┃ ・お客さまを行動させるためのきっかけづくりをどこに入れるかを考える
┃
┃ ・お客さまの情報をどのようにつかみ次につなげるかを考える
┃
┃ ・・・などなど。
┃
┃
┃
┃ これらを組み立てていくことがホームページのデザインというものです。
┃
┃ いわゆるグラフィックデザインのことだけではないんです。
┃
┃
┃
┃ グラフィックデザインの要素については、
┃
┃ たとえば、タイトルデザインとか,ロゴデザインとか,ページデザインとか、
┃
┃ デザインすることはたくさんありますが、
┃
┃ 実作業の割合は、全体の2〜3割程度でしょう。
┃
┃ トータルイメージづくりとか。
┃
┃
┃
┃ はじめにきちんと決めておくことは《伝えたいこと》の内容と《伝え方》、
┃
┃ そして、その《見せ方》です。
┃
┃ もっといえば、これらすべてについての「自分の考え」を固めておくことが
┃
┃ 何よりも重要なことです。
┃
┃
┃
┃ ホームページの作り方を解説した本はたくさんありますが,
┃
┃ ソフトの扱い方を解説しているにすぎません。
┃
┃ いざ「自分でつくる」となったら
┃
┃ 内容はすべてを自分で決めていかなければなりません。
┃
┃
┃
┃ ですから、
┃
┃ 「デザインをする前にすること」としてお話ししているわけです。
┃
┃
┃
┃ 広告づくりの現場でも同じように表現の実作業に入る前に、
┃
┃ 今の状況を理解するためにさまざまなことを、
┃
┃ 調べ、研究し、検討しながら進めているのです。
┃
┃
┃
┃ いかに お客さまの“心”をつかむか?
┃
┃
┃
┃ そのための準備と理解してください。
┃
┃
┃
┃ ここで、ホームページと広告の違いについて理解しておきましょう。
┃
┃ Web についての解釈はまだまだこれからも試行錯誤が続くと思います。
┃
┃ それだけ進化、発展が激しく制作の現場で確立した方法論はまだありません。
┃
┃ ホームページは、
┃
┃ あなたの“ショールーム”と言い換えることができると思います。
┃
┃
┃
┃ 広告は一般に不特定多数の人=「知らない人」に「知らしめる」、
┃
┃ つまり、告知する意味が強いのですが、
┃
┃ ホームページの告知の力は従来のメディアのような期待はできませんが、
┃
┃ そのかわりもっと直接的に語りかけることができる力があります。
┃
┃ ホームページに訪れる人たちは、
┃
┃ ちょうどショールームに入ってくる人たちと同じように捉えられるでしょう。
┃
┃
┃
┃ あなたが、ショールームを訪れたお客さまに対して、どう対応していくか?
┃
┃
┃
┃ それがホームページづくりにも通じることだと思います。
┃
┃
┃
┃ そこを押さえて《ラフスケッチ》を見直してみてください。
┃
┃ より具体的な全体の設計図として検討できることと思います。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ コピーライティング・・・・・・・・・・・・・◇ 風嶺 瞭 KAZAMINE RYO
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━━━ 「 新 聞 の 見 出 し 」 に 見 る 誘 惑 テ ク
┃
┃
┃ さて、他の講師陣も口を揃えるように説明していますが、
┃
┃
┃ 本当に稼ぎたかったら
┃
┃ “HPづくりのテクニック”が先にありき、
┃
┃
┃ ではなくて、
┃
┃
┃ 「どんな魅力」を伝えるために、
┃
┃ 「どんな内容」とするのかを“考えること”が最優先!
┃
┃
┃ であることは、もう理解できましたよね。
┃
┃
┃ そのために、どのように考えればよいのか、
┃
┃ どのように考える素材を集めたらよいのか、
┃
┃ また、どのようにまとめ、どのような魅力を持たせればよいのか、
┃
┃ 以上についての基本的な話を前回までしてきたつもりです。
┃
┃
┃ 《伝えたい魅力》を文字レベル(文章レベル)で表現するのが、
┃
┃ コピーライティングであり、キャッチコピーです。
┃
┃
┃ 皆さんのサイトを閲覧していて思うのは、
┃
┃
┃ 核心が埋もれて、ちょっと見では、その特異性がわからないものが多い
┃
┃
┃ ということ。
┃
┃
┃ 特に、文字レベルにそれを強く感じるのです。
┃
┃
┃ 多少見栄えの悪いデザインであっても、
┃
┃ 魅力的な、気持ちをグッと引き寄せるキャッチフレーズが、
┃
┃ ポンっ!と小気味よい印象を伴って、
┃
┃ 一等目立つところにレイアウトされていたりすればいいのですが、
┃
┃ それが、ない。
┃
┃
┃ 勝負以前の問題で、
┃
┃ HPとしてはスマートに構築されていても、
┃
┃ 「あなたはどちら様でしたっけ?」と記憶に全く残らない。
┃
┃
┃ たまに我慢をして、じっくり細かい文字がビッシリと詰まった文章を、
┃
┃ 目をチカチカさせながら読んでみると、
┃
┃ 「へぇ〜」とか「なるほど!」「そうだったのか!!」と
┃
┃ 有益な情報がたんまりとあるなんてことも。
┃
┃
┃ しかし、それはごくまれなケースで、
┃
┃ 歳末の福引きのごとく、期待感だけを育みながら長蛇の列に並んで、
┃
┃ 末等のポケットティッシュだけに終わるようなサイトの多いこと。
┃
┃
┃ したがって、そういった面構えのホームページは、
┃
┃ 誰某の御墨付きでもない限り訪問しようとは思わないし、
┃
┃ ネットサーフィンの途中で出会っても馬耳東風どころか素通り状態。
┃
┃ 検索エンジンで上位に登場しようが、関係ありません。
┃
┃
┃ それどころか、検索エンジンに登場したタイトルを見て、
┃
┃ 「あっ、こりゃ、内容の薄いものだな」とか、
┃
┃ 「これは一握りの仲間内だけの掲示板だな」とか、
┃
┃ 「これは、寂しがりやのブログの類か」と、
┃
┃ すでに勘づかれてしまう状況にきているのです。
┃
┃
┃ 本当に「売りたい」のなら、「伝えたい」のなら、
┃
┃ 考えて《実力=魅力》をつけるしかないのです。
┃
┃
┃
┃ この「シンプルデザイン」をテーマとした
┃
┃ メルマガ講座の趣旨は、ここにあります。
┃
┃
┃ 本当に魅力的なものは、最新技術に頼らずとも、
┃
┃ 《伝え方=表現》さえ間違わなければ、伝わるのです。
┃
┃
┃ そして、それを左右するのが《考える力量》なのです。
┃
┃
┃ メディア選択はできているわけですし、
┃
┃ 情報を流すネットワークの開拓にしても、
┃
┃ 魅力を持っているかいないかで大きく変わってきます。
┃
┃
┃ 卑近な例でいえば、口コミやうわさ話などは、
┃
┃ 魅力的なものであればあるほど、
┃
┃ どんな手段で阻止しようとしても伝わっていきますよね。
┃
┃
┃ さて、前書きが前書きでなくなりましたが、
┃
┃ 前号でお話した
┃
┃
┃ ターゲットを引き付ける展開を図っていく中で、
┃
┃ 全体を理解させるための必要要素を細かく散りばめていく―
┃
┃
┃ 手法を、皆さんが毎日触れる新聞を素材に、簡単に説明したいと思います。
┃
┃
┃ 現時点でもっとも新しい11月18日の読売新聞夕刊から。
┃
┃ 1面トップに、いきなり
┃
┃
┃ 『 新 築 ホ テ ル 営 業 中 止 』
┃
┃
┃ の縦書き文字が、黒地に白ヌキの太いゴシック系の書体で印刷されています。
┃
┃ その上に、こちらは横書きで、
┃
┃
┃ 『 耐 震 強 度 偽 装 』
┃
┃
┃ の文字が、先ほどの見出しより1/4ぐらいのサイズの、
┃
┃ 細いゴシック系の書体で乗っかっています。
┃
┃ このニュースをすでに昼間の報道で知っている方でも、
┃
┃ いきなり『新築ホテル営業中止』の文字がバーンと目に飛び込んできたら、
┃
┃ 「えっ?いったい何が、またあったんだ」と未知の出来事に
┃
┃ 好奇心を書き立てられることでしょう。(実際に私がそうでした…とほほ)
┃
┃ このフレーズなら、すぐには「どうせ、あのニュースのことだろ」
┃
┃ とはなりにくいはずです。
┃
┃ しかし、よく記事を読めば、すぐに合点がいくように構成されているのです。
┃
┃
┃ 的確な報道の義務と使命を保ちながらも、
┃
┃ 読者を引き付け、新聞の魅力を維持しようとの意図がうかがえる見出しです。
┃
┃
┃ 『新築ホテル営業中止』の見出しに、
┃
┃ 新聞を手に取ったり、内容を読み始めてくれれば、
┃
┃ 執筆した記者の狙いは達成されたことになるのです。
┃
┃
┃ 分かりやすさを追求するなら、
┃
┃
┃ 『 千 葉 県 ・ 建 築 設 計 事 務 所 / 耐 震 強 度 を 偽 装 』
┃
┃ 『 新 築 ホ テ ル が 営 業 停 止 に 』
┃
┃
┃ が見出しになってもおかしくないのに。
┃
┃
┃
┃ キャッチコピーの作成手法も同様なのです。
┃
┃
┃
┃ キャッチを見た読み手に、どのような行動をさせるか。
┃
┃ そのために魅力あるフレーズとなっているか。
┃
┃ 内容をしっかりと間違いなく伝えられているか。
┃
┃
┃
┃ 新聞の見出し部分には、このほか、
┃
┃ 『 京 王 電 鉄 が 運 営 「 安 全 を 優 先 」 』
┃
┃ の文字がメインの見出しの左横下に配置され、
┃
┃ 営業中止が決まったホテルの写真をメインビジュアルに、
┃
┃ 記事本文が加えられている。
┃
┃
┃
┃ さらに詳しい内容については『関連記事19面』の文字が、
┃
┃ 記事本文最後に目立つようにゴシック系の書体で添えられている。
┃
┃ どこまでも「伝えたいところ」に引っ張ろうとする工夫が
┃
┃ 凝らされているわけです。
┃
┃
┃
┃ このように、普段何気なく読んでいる新聞にも、
┃
┃ 効果あるキャッチコピー作成のヒントが隠されているのです。
┃
┃
┃
┃ 新聞だけでなく、皆さんのまわりにある文章はほとんどが
┃
┃ この法則に則ったものばかり。
┃
┃
┃
┃ 次回も実例をご紹介しながら説明していきましょう。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ 写真撮影・画像処理 ・・・・・・・・・・◇ 倉田 浩路 KURATA HARUMICHI
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━ デ ジ タ ル カ メ ラ 撮 影 術 〜 基 礎 編
┃
┃
┃ 前回はカメラ選択の注意点をお話ししましたが、
┃
┃ 理解できましたでしょうか。
┃
┃
┃
┃ 機能面を話し始めて気がついたのですが、
┃
┃ デジタルカメラは、フィルムで撮影するカメラに比べて、
┃
┃ 長持ちさせることができないシロモノであると。
┃
┃
┃
┃ 今までだったら、メンテナンスさえしっかりとしていれば、
┃
┃ いつまででも使用できて、
┃
┃ 2代3代と受け継がれたお古でも最新のフィルムが使用できたので、
┃
┃ 10年、20年前のカメラなのに、
┃
┃ 超微粒子の高画質プリントを作ることができました。
┃
┃ しかしながら、今のデジタルカメラの最大の欠点は、
┃
┃ まだ発展途上にあるため、数年しか持たない―つまり、長持ちしないのです。
┃
┃ (コンピュータ化したカメラを、
┃
┃ 生産コスト面からしか作れないメーカーが大多数となったからでしょうか)
┃
┃
┃
┃ 中身は、発展途上のコンピュータなので、
┃
┃ 「何がよいか」と問われれば《最新のモデル》となります。
┃
┃
┃
┃ しかし、意外に早く壊れるのには正直びっくりです。(昔より賞味期限が短い)
┃
┃ 10万円クラスの中級カメラから80万円クラス以上でも、
┃
┃ モデル撮影、報道(特にスポーツ関係)のカメラマンたちになると、
┃
┃ 一般の方々の10年以上分くらいのシャッ ター回数を、
┃
┃ 半年から1年くらいで押してしまうのでメンテナンスは日常茶飯事。
┃
┃ それでもシャッター駆動部分や絞りなどの交換が必要で、
┃
┃ 必ず1〜2回は交換しています。
┃
┃
┃
┃ こうした機械的な部分であれば交換も簡単だし、
┃
┃ 部品代もたいしたことはないのですが、
┃
┃ コンピュータのメインボード(カメラも今はコンピュータで制御)が壊れると、
┃
┃ ものすごく高額になり、新品を買った方が良いこととなります。
┃
┃
┃
┃ どうにもデジタルカメラが好きになれないもんで、
┃
┃ 否定的になりがちな説明でしたが…。
┃
┃ デジタルカメラやコンピュータの便利で優れた点を上手に使って、
┃
┃ 時間をより有効活用していかなければいけませんね。
┃
┃
┃
┃ いまさらなんですが、デジタルカメラの説明をしていて、
┃
┃ 一つ気になることがあります。
┃
┃
┃
┃ それは、専門用語の件です。
┃
┃
┃
┃ 皆さんがどこまで知っていて、どこから判らないのか、
┃
┃ 個人差もあるとは思いますが、
┃
┃ 一応、私が捉えた平均値で話を進めさせてください。
┃
┃ もし、判らないときは調べてください。
┃
┃ それでも理解できないときは、遠慮なく質問のメールをください。
┃
┃
┃
┃ では少しずつ本筋に入っていきますよ。
┃
┃
┃
┃ 実際に撮影して仕上がりを見てがっかりしたり、
┃
┃ 写っているけど、自分が撮ろうと考えた構図とは違う、
┃
┃ などといった経験はないですか。
┃
┃
┃
┃ なぜそうなるのか。
┃
┃
┃
┃ 皆さんが対象物を見るときの気持ちによって目は、
┃
┃ 広角レンズだったり、標準レンズだったり、
┃
┃ 中焦点あるいはそれ以上の望遠レンズ的な視野で、
┃
┃ 対象を見ながらシャッターを切ってるのですが、なぜか仕上がった画像は、
┃
┃ 小さかったり画面の端にいたり、ピントがはずれていたり、
┃
┃ とイメージ通りではない。
┃
┃
┃
┃ 主題となるべき要素を強調できないのは、なぜか?
┃
┃
┃
┃ ○被写体に対して、撮影者が遠いために起こる
┃
┃ → 主題にはできるだけ近づいて撮る
┃
┃
┃
┃ たとえば、友人あるいは家族との記念写真を撮るとします。
┃
┃ 自分が持っているカメラのファインダーを覗いているんだけど、
┃
┃ 望遠レンズ的にカメラ前の人たちを捉えてみると、
┃
┃ みんなの周囲に不要な物がいっぱい写っていて、表情がよく見えない。
┃
┃ こういう状況であれば、あと2〜3歩か、1〜2メートルほど、
┃
┃ 被写体に近づけば、みんなの楽しげな表情を写せるのです。
┃
┃
┃
┃ 今のカメラはだいたいズームレンズ付きですが、
┃
┃ それでも起こりがちな失敗例です。
┃
┃
┃
┃ ○画面上で、主題と背景が解け合ってしまう
┃
┃
┃
┃ この場合も、中心とする主題に神経が集中しすぎてしまい、
┃
┃ その背景に何があるかをキャッチできずに、
┃
┃ 頭の上から何か生えてるような木とかの線が写ったり、
┃
┃ 首の辺りに水平線が横切ってしまったり、
┃
┃ あるいは煩雑な中にいるように写ってしまうのですが、
┃
┃ シャッターを切る一瞬の間にもちょっと気を配り、目線を変えて、
┃
┃ 少し下とか上とか横にずれるだけで主題が浮いてくるのです。
┃
┃
┃
┃ こうしたことを回避するためにどうするか?
┃
┃
┃
┃ プロのカメラマンがシャッターを多く押すのはなぜか?
┃
┃
┃
┃ それは、シャッターチャンスは2度とないから、
┃
┃ 考えられること を、できることを、そのときにやっておかないと、
┃
┃ 同じシチュエーションは2度と作れないし来ないからです。
┃
┃
┃
┃ 皆さんも、これからは何を撮るにしても一方向からでなく、
┃
┃ いろいろな角度から撮影するように心がけてください。
┃
┃
┃
┃ もう一つ加えるなら、露出を変えて撮ってみてください。
┃
┃ 適正露出が良いか、少し明るく撮った方が良いか、
┃
┃ あるいは、暗めに撮った方が良いかを試してみてください。
┃
┃
┃
┃ 普段はカメラ任せで、
┃
┃ シャッターは一回しか押さないという方もいると思いますが、
┃
┃ 露出を変えることで主題の見え方が全く違ってくることが ある、
┃
┃ ということを理解してもらえればと思います。
┃
┃
┃
┃ この点でデジタルカメラは、幾ら撮ってもすぐに確認でき、
┃
┃ メモリが許す限りフィルム代の心配なく撮れるわけですから、
┃
┃ 遠慮なくバンバ ン!ガンガン!シャッターを切って見比べてください。
┃
┃
┃
┃ 気に入らなければ、違う方法で撮り直せば良いのです。
┃
┃
┃
┃ この手間だけは「面倒くさい」などといわずに、いろいろ試すことが大事です。
┃
┃ 失敗と思ってもあきらめずにチャレンジしてください。
┃
┃ フィルムの頃は「フィルム代だ」「現像代だ」「プリント代だ」と、
┃
┃ 費用がかさみましたが、フィルム代・現像代がいらず、
┃
┃ 撮ったその場で結果を知ることができるデ ジタルカメラの
┃
┃ 最大の利点を思う存分利用する。
┃
┃
┃
┃ 何でも言えることですが、事前の計画が一番大事ですね。
┃
┃
┃
┃ 計画を立てることによって、「主題は?」「背景は?」「色合いは?」など、
┃
┃ 全体の画面構成に何が必要か、そのための準備をどうするか等を決めておけば、
┃
┃ スナップを撮るにしても、静物を捕るにしても、
┃
┃ ファインダー画面の中に、何が必要で、何がい不要かを判断できます。
┃
┃
┃
┃ 昔のように、すべてが手動ではなく、
┃
┃ 露出も、シャッター速度も、ピント合わせも、
┃
┃ すべてが自動化されているカメラ任せではなく、
┃
┃ 説明書をよく読んでカメラの手 動化できる部分を選んで、
┃
┃ いろいろと条件や設定を変えて撮影して結果を見比べてください。
┃
┃
┃
┃ 静的な被写体は、特にいろいろ試すことができるので、
┃
┃ 今回話したように露出を変えて、《明るめ》《適正》《暗め》とか、
┃
┃ 上から、横から、斜めから撮ってみる。
┃
┃
┃
┃ 動体は、シャッターを遅く、
┃
┃ 《適正》と《より早く》とを組み合わせて撮り比べてください。
┃
┃ いろいろと表情が違って写るのがきっと理解できます。
┃
┃
┃
┃ この辺りができるようにならないと、画像処理はできませんよ。
┃
┃
┃
┃ とにかくいろいろなシチュエーションを経験しないと、
┃
┃ 思っているイメージの画像(絵づくり)ができないので頑張ってみてください。
┃
┃
┃
┃ 撮影経験を積むことによって、
┃
┃ 自分がどんなところで躓くかが見極めることになり、
┃
┃ 撮影技術の修正ポイントがはっきりとしてきます。
┃
┃ 頑張ってください。
┃
┃
┃
┃ 文章で書き記すのはなかなか大変ですが、理解できましたか?
┃
┃
┃
┃ 来週は、今回同様、途中脱線しながらになると思いますが、
┃
┃ 『ライティング』の話を中心に進めたいと考えています。
┃
┃ 間に合うようであれば、比較できるような画像データを、
┃
┃ 実際に別の場所でお見せして、より理解しやすく説明したいと思います。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ プランニング ・・・・・・・・・・・・・・◇ 西 佳宏 NISHI YOSHIHIRO
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━ 続・ネットで成功するための、『システムとノウハウ』
┃
┃
┃ ネットで成功するための、『システムとノウハウ』続きです!
┃
┃
┃
┃ 前号で、自分の決めた道を1年は続けましょうと書きました。
┃
┃
┃
┃ どんなメディアで続けようと思いましたか?
┃
┃
┃
┃ 当然、前号のお話はアフィリエイトに関してでしたから、
┃
┃ 今、流行りのMTブログ、
┃
┃ もしくは通常の無料ブログを連想されたでしょうね。
┃
┃
┃
┃ ここで、流行りについて、ちょっと考えてみましょう。
┃
┃
┃
┃ ブログはホームページを作るより簡単に始められますね。
┃
┃
┃
┃ 文章を書くだけでページが自動更新されますし、
┃
┃ 過去ログとしてリンクを通じて残って行きます。
┃
┃
┃
┃ あなたはアフィリエイトの仕組みを理解するだけで、
┃
┃ ちょっとしたネットショップを立ち上げることができます。
┃
┃
┃
┃ でも、前号でお話したオリジナルノウハウという点からすると、
┃
┃ 同じイメージのショップが現れる危険性も含んでいますから、
┃
┃ オリジナル性の観点からすると、
┃
┃ マイナスに転ぶ可能性を秘めているわけです。
┃
┃
┃
┃ MTブログのように流行れば流行るほど、
┃
┃ 同じイメージのショップが増殖されて行きます。
┃
┃
┃
┃ カスタマイズできれば、見た目を変えられますが、
┃
┃ 流行りに乗った初心者には無理ですね。
┃
┃
┃
┃ アクセスアップを図って、来訪者の目にとまっても、
┃
┃ 「あれっ? どこかでみたぞ!」と思われたり、
┃
┃ 「またこれか!」と思われてしまっては、
┃
┃ せっかく100ページのショップを作っても、
┃
┃ 読み込んでもらえないという結果になるかも知れません。
┃
┃
┃
┃ 流行りとは便利だから流行るんですが、
┃
┃ 「便利」イコール「目的の達成」ではないのです。
┃
┃
┃
┃ あなたが新しいことを始めるときは、
┃
┃ プラスの面とマイナスの面を、きちんと考えてください。
┃
┃
┃
プラスだけで考えないで欲しいのです。
┃
┃
┃
┃ ここで、その思考法を伝授しますね。
┃
┃
┃
┃ 紙にTの字を書いて、左をプラス、右をマイナスにして、
┃
┃ 考え得る全てをピックアップして比較してください。
┃
┃
┃
┃ プラス マイナス
┃ ────────────────────────────────
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃ │
┃
┃
┃
┃ こんな簡単な表です。
┃
┃
┃
┃ ここに書き出すことによって、客観的に判断できるようになります。
┃
┃
┃
┃
┃
┃ 話をブログからホームページへ変えます。
┃
┃
┃
┃ ホームページソフトを使いこなせるようになるには、
┃
┃ 少なくとも10日以上かかりますね。
┃
┃ 人によっては数カ月という人もいるでしょう。
┃
┃
┃
┃ さらに、使いこなせるようになる前に、諦めてしまう人が多いと思います。
┃
┃
┃
┃ 資金があれば、専門家に作ってもらう手もありますが、
┃
┃ 企業のイメージサイトや趣味のサイトなら、いざ知らず、
┃
┃ ネットショップは自分で更新作業ができなくては意味がありません。
┃
┃ そこまで頼んだらお金がいくらあっても足りないでしょうから。
┃
┃
┃
┃ みんな、まずはブログから入っても、
┃
┃ 最後はオリジナルのホームページを持ちたい、作りたい、
┃
┃ きっと、そうなるはずです。
┃
┃
┃
┃ 「伝える」という行為によって、
┃
┃ 何かしらのリアクションを求めるのであれば、
┃
┃
┃
┃ ◆ オ リ ジ ナ ル の イ メ ー ジ
┃
┃ ◆オ リ ジ ナ ル の 視 点
┃
┃ ◆オ リ ジ ナ ル の ノ ウ ハ ウ
┃
┃ ◆オ リ ジ ナ ル の 文 章 etc
┃
┃
┃
┃ 全ての行為に「オリジナル」が加わらなくては、アピール力が弱いのです。
┃
┃
┃
┃ 何かを始めるときは必ず、
┃
┃ あなただけの「オリジナル」を追求してくださいね。
┃
┃ わたしも、そのための「ヒント」を出し続けますから。
┃
┃
┃
┃ ネットで成功するには、
┃
┃ 『オリジナルシステム』と『オリジナルノウハウ』を
┃
┃ 作り上げるのが、いちばんの早道ですよ。
┃
┃ 他にはないということですから。
┃
┃
┃
┃ ここで、この「釘サイ塾」(勝手に略しますが)の読者にプレゼント!!
┃
┃
┃
┃ アフィリエイトサイト用テンプレートを差し上げます!
┃
┃ e-Book形式になっていますので、
┃
┃ 下記よりダウンロードして活用してください。
┃
┃
┃
┃ カスタマイズを忘れずに! オリジナル性を追加してくださいね。
┃
┃
┃
┃ http://simple.sub.jp/eBook_10p.pdf
┃
┃
┃
┃
┃
┃ ※やる気とノウハウ習得の早道
┃
┃ http://simple.sub.jp
┗
☆ インフォメーション-------------- 当メルマガの活用法と塾生(購読者)特典
何名とは公言できませんが、読者数、大台突破です。パチパチパチ!
これもひとえに皆様のお力添えの賜物と感謝している次第です。
本当ですよ。
きっと何人かに1名の割合で友人などに進めてくれた方が
いたに違いありません。
ありがとうございます。
さて、講師陣も脂が乗ってきたようで、
軒並みボリュームアップの内容となっていますが、
最後まで読んでくださり、うれしく思っています。
皆さんからのメールや質問も、
引き続き受け付けていますので、フォーラム開設まで、
いや、開設後もどんどんお寄せください。
ぜひ「こんなことを教えてほしい」「私のサイトを見てアドバイスを」等の
ご要望やご意見を遠慮なくどうぞ。
送信先は、編集責任者である“風嶺”へ。
▽継続購読していただくための塾生サービスの紹介!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
├─その1:サイトと連動したビジュアルな展開により、 ┃
┃ ┃
┃ イラストや図を活用して、 ┃
┃ ┃
┃ 見て理解できるわかりやすさを追求! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その2:塾生(購読者)専用のフォーラム(掲示板)を開設! ┃
┃ ┃
┃ わからない部分や聞きたいことを、ピンポイントに講師に ┃
┃ ┃
┃ 尋ねることができます!! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その3:フォーラムを通しての塾生間交流や情報収集もOK! ┃
┃ ┃
┃ 人脈づくりにも有効に活用していただけます。 ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その4:仲間の存在により、モチベーションの維持だって図れます! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その5:ホームページやインターネット関連にとどまらず、 ┃
┃ ┃
┃ グラフィックデザイン、広告活動、SP戦略など、 ┃
┃ ┃
┃ 広告・広報に関する幅広い専門知識の吸収も可能です。 ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その6:本格的にしたいけど自分では・・・という方には、 ┃
┃ ┃
┃ 実際に講師スタッフがお仕事の依頼を受けることも可能。 ┃
┃ ┃
┃ 塾生割引有り? ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
フォーラムの開設(ID、パスワードが必要)のお知らせを、
次回いたします。お楽しみに。
それでは来週、またお会いしましょう。
━o(^-^)○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「釘づけサイトのデザイン塾」(原則として毎週金曜発行)
企画・発行:クー・アートメディア http://www.ku-am.co.jp/
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-4-1-103
編集者・お問合せ:風嶺 瞭 kw800096@fsinet.or.jp
(C) 2005 Ku: Art Media Inc. All rights reserved.
掲載の記事の無断転載を禁じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |