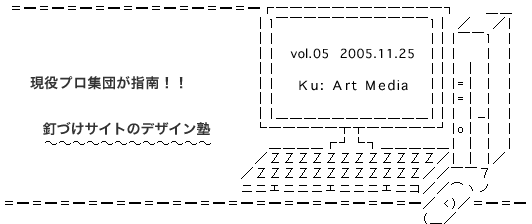| 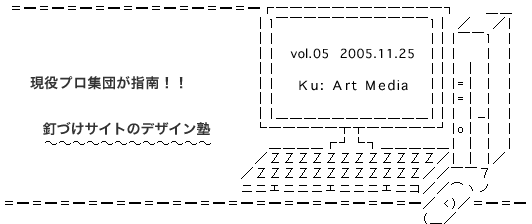
━ CONTENTS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ イントロダクション --------------------- 既成概念や固定観念にサヨナラ
★ デザイン ------------【ラフスケッチで来訪者をしっかりイメージしよう】
★ コピーライティング ------------【精神錯乱でアピールポイントを探る?】
★ 写真撮影・画像処理 ----------------------【ロケーションハンティング】
★ プランニング -----------------------【『売るためのスキル』を磨こう!】
☆ インフォメーション ----------------- 塾生フォーラム開設のお知らせなど
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ 今週のイントロダクション ----------------------------------------------
文字要素も、ビジュアルのひとつの要素として捉える。
デザインというと、たいていの方は、
なぜか文字要素を、のけものにするのです。
反対に、新人のコピーライターの場合、
文字以外の要素のことを、まるで無視するかのように、
いっぱい文章を書いてしまう人がいます。
まあ、それが得意なので仕方ありませんが、
人間は、シックス・センスもありますが、五感を駆使して生きている動物です。
情報を基に考えて判断し、結論を導き出す能力にすぐれていますが、
この五感だか、六感に訴えかけることが、
すべての要素にとって有効なのです。
ポスターやチラシなら、視角に訴える“色彩”はもちろん、
香りを放つインクや、触感に訴える立体感を表現するインクまで
開発されているのです。
インクは、ビジュアルを表現するもの。
なんて固定観念に捕われていると、より高い訴求効果は得られません。
文字は情報を伝えるだけでなく、ビジュアルの一端、
場合によっては、ビジュアルそのものになるケースもあるのです。
情報として内容を伝達するだけでなく、
ビジュアルとして何かを訴えかけることもできるのです。
相田みつおの書のように。
人に注目されるホームページにしたい。
そう思ったら、既成概念、固定概念を捨て去ることです。
他者より「売れるサイト」「伝わるサイト」にするためには、
少しでも、他者にはない魅力をプラスすることです。
わたしたちは、
あなたをネットビジネスにおける、その他大勢、つまり、
「ひな形」として埋もれさせたくはないのです。
さあ、今回も、あなたのサイトを、
目立つサイトに変えるための講義をはじめましょう!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・◇ 倉田 浩孝 KURATA HIROTAKA
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━ HPデザイン前にすること(5)
┃
┃ ラ フ ス ケ ッ チ で 来 訪 者 を し っ か り イ メ ー ジ し よ う
┃
┃
┃ みなさん こんにちは! 今日も張り切っていきましょう!
┃
┃ 前回,ホームページは,
┃
┃ あなたの「ショールーム」と言い換えられるといいました。
┃
┃ ここでは,「ショールーム」という考え方を簡単にご説明します。
┃
┃
┃
┃ ホームページのトップページは「ショールーム」の入り口と同じです。
┃
┃ ご自分を「ショールームに来た人」の立場で見直してみてください。
┃
┃ ラフスケッチに描き込んだいろいろなアイデアを検討し、磨き上げるために、
┃
┃ ご自分がどのように迎えられたら満足できるだろうか?
┃
┃ 何が「心地よいか?」を整理しましょう。
┃
┃
┃
┃ 大事なことは:
┃
┃ ・あなた=来た人が欲する情報がすぐに見つかるか?(→コンテンツの内容)
┃
┃ ・欲する情報(商品)が見やすく整理されているか?(→コンテンツの整理)
┃
┃ ・案内がわかりやすく,迷わずに見て回れるか? (→見やすい導線)
┃
┃ ・あなたの希望に沿った対応でよく話を聞いてくれたか?
┃
┃ (→情報の発信と顧客情報収集)
┃
┃
┃
┃ ざっとこんなところが満たされたら、
┃
┃ あなたは「来た甲斐があった」と思えるのではないですか?
┃
┃
┃
┃ あなた=「ショールームに来た人」は大事なお客さまです。
┃
┃ 何かを求めて探しにきていますし、興味を持ってきます。
┃
┃ 同時にお店にとっては,直接お客さまの情報をゲットできるチャンスですし、
┃
┃ 伝えたい情報をきちんとお話しできる絶好の機会(接点)です。
┃
┃ お客さまには満足していただいて,次の行動につながったら最高ですよね。
┃
┃
┃
┃ このような視点でラフスケッチを見直せば、
┃
┃ いろいろな角度から検討できるようになります。
┃
┃
┃
┃ 《ホームページをデザインする》全体の流れは次のようになります。
┃
┃ ・企画立案……………伝えたい情報を把握して企画を立てる
┃
┃ ・ウェブサイト設計…お客さまの導線を明確にして基本的なチャートをつくる
┃
┃ ・画面デザイン………上記の設計(ラフスケッチ)に基づいてデザインする
┃
┃ ・レイアウト…………各画面デザインに素材をレイアウトする
┃
┃ ・テスト&修正………ユーザー環境を想定して動作テストと修正を繰り返す
┃
┃
┃
┃ 先に描いていただいたラフスケッチは
┃
┃ 「企画立案」の部分をかたちに表したものです。
┃
┃ これで、企画内容それ自体をしっかり把握することができます。
┃
┃ ラフスケッチで「必要項目」を洗い出し(=検討)します。
┃
┃ そしてお客さまを釘づけにするために「必要な項目」を洗い出し、
┃
┃ 「洗い出した項目」に対して細かい情報を洗い出していきます。
┃
┃
┃
┃ たった1枚の白い紙に描き込まれた情報の生の姿=ラフスケッチは
┃
┃ 少しずつかたちを変えながら磨かれていきます。
┃
┃ ホームページの構想がまったく見えなかったところが
┃
┃ はっきり姿を現すでしょ?
┃
┃
┃
┃ ラフスケッチはこの1枚だけではありません。
┃
┃ 次に描くのはウェブサイトの設計書です。
┃
┃ ラフスケッチと同様に大きな紙にトップページから
┃
┃ どのページに展開していくかを流れとして描いていきます。
┃
┃
┃
┃ 全体の流れが描けたら,その導線をよく見直し、検討してみてください。
┃
┃
┃
┃ 以上で今日の講義は終了、お疲れさまでした。
┃
┃
┃
┃ 本当はもっと簡単にシンプルにデザインしたいなぁ?!って
┃
┃ 思いませんか?
┃
┃ こんなことぐだぐだ聞いているより
┃
┃ どこからか気の利いたテンプレートを持ってきて
┃
┃ 必要なことを入力したら良いじゃん!
┃
┃ そしたらあっという間にできちゃうでしょ?
┃
┃
┃
┃ その通りですね。
┃
┃ それが一番簡単で,かたちだけ早くホームページができる方法です。
┃
┃
┃
┃ ですが、気の利いたテンプレートを活かして
┃
┃ 独自に自分でホームページをつくるときでも
┃
┃ 「デザインを考える」姿勢は忘れないようにしてください。
┃
┃ 訴える力が違ってきますから・・・
┃
┃ オリジナリティ溢れるホームページになりますよ。
┃
┃
┃
┃ そしてしっかり考えて作り上げることができれば
┃
┃ それはそれは、大きな自信になること間違いなしです。
┃
┃ 現役プロ集団が指南!! 釘づけサイトのデザイン塾は
┃
┃ そのために開いたのですから。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ コピーライティング・・・・・・・・・・・・・◇ 風嶺 瞭 KAZAMINE RYO
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━ 精 神 錯 乱 で ア ピ ー ル ポ イ ン ト を 探 る?
┃
┃
┃ 皆さんは、初対面の人と出会ったとき、
┃
┃ どのような挨拶をします?
┃
┃
┃
┃ プライベートなケース、ビジネスシーンで、
┃
┃ 仲介者がいる、自ら探し求めて…など、状況にもよると思いますが、
┃
┃ 各々のケースで「どう自分をアピールすればよいか」を考えて、
┃
┃ 対処しているのではないでしょうか?
┃
┃
┃
┃ アピールするからには、
┃
┃ ご自分の《長所》が、より効果的にしたいと考えているはずですよね。
┃
┃
┃
┃ では、皆さんは、どのくらい、ご自分の長所を把握できているのでしょうか?
┃
┃
┃
┃ 先に述べたように、対面時には、プライベートやビジネスなど、
┃
┃ さまざまなケースがあります。
┃
┃
┃
┃ 皆さんは、きっと、そのときの“ケース”に合わせて、
┃
┃ 最も効果を発揮する、ご自分の《長所》を最優先に“自動選択”して、
┃
┃ 相手にアピールしていると、思っているはずです。
┃
┃
┃
┃ 真面目さが定評の方、笑顔が魅力的な方、元気が売りの方、
┃
┃ 知識や情報通の方、冗談の上手な方、飲みが得意な方、
┃
┃ 段取りに力を発揮する方、口より行動の方…などなど。
┃
┃
┃
┃ 広告・広報活動はもちろん、
┃
┃ コピーを含めたサイトデザインでは、このポイントが最重要なんですね。
┃
┃
┃
┃ 先週の“新聞記事の実例”も然り、です。
┃
┃ 衆目を集めるのが“得意”なのが、新聞です。
┃
┃ その《長所》を発揮して、しっかり読者のハートをつかむ。
┃
┃
┃
┃ では、新聞には、それしか《長所》がないのかというと、
┃
┃ 当然、知識や情報通であるし、真面目さはもちろん売りです。
┃
┃ かといって、堅物かというと、
┃
┃ 芸能ネタやスポーツネタもそれなりに好きですし
┃
┃ 野外のハイキングに誘ってくれたりもします。
┃
┃
┃
┃ いろいろな《長所》を持っているんですね。
┃
┃ そして、それを巧みに、ケース・バイ・ケースで使いこなしているわけです。
┃
┃
┃
┃ ここで、先ほどの質問に戻ります。
┃
┃ 皆さんは、どのくらい、ご自分の《長所》を把握できているのでしょうか?
┃
┃
┃
┃ 残念ながら、この質問にある程度、答えられないと、
┃
┃ アフィリエイトはうまくいかないかもしれません。
┃
┃
┃
┃ 自分の《長所》が客観的に把握できていないのに、
┃
┃ おすすめする“商品”の《長所》を、
┃
┃ どれだけ相手に伝わるように把握できるのでしょうか?
┃
┃
┃
┃ 他者と自己との区別を付けた上で、
┃
┃ その自己が「よい」と思ったものを、
┃
┃ 異なる他者にどのようにメッセージすれば、首をタテに振ってくれるか。
┃
┃
┃
┃ そのメッセージの“突撃隊長”がキャッチフレーズなのですから、
┃
┃ ご自分や“商品”の《長所》に、
┃
┃ どのようなものが、どれくらいあるのかがつかめていないと、
┃
┃ 独善的な“言葉の羅列”、マスターベーションで終わってしまいます。
┃
┃
┃
┃ 「○○な人たちに、この“商品”の●●という《長所》を、
┃
┃ 私の□□な《長所》を活かしてメッセージすれば、伝わるのではないか。
┃
┃ いや、○○な人たちではなく、◎◎な人たちに向けたほうがよいのでは?」
┃
┃
┃
┃ 製品開発、販売戦略、広告戦略は、上記のような思索を通して、
┃
┃ 編み上げられていくわけですから、
┃
┃
┃
┃ 自他ともに認める“おのれのいいトコ”がどこか、
┃
┃ “商品”の“よいトコ”が把握できていなければ、柱のない家のようなものです。
┃
┃
┃
┃ 「そうはいっても、このケースはどの《長所》を優先すればよいのだろう?
┃
┃ だいたい《長所》なんてそう幾つもあるものなのかしら?」
┃
┃
┃
┃ それを探し出す方法を、今回はお教えしましょう。
┃
┃
┃
┃ 『ブレインストーミング』という発想法です。
┃
┃
┃
┃ ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
┃
┃ 本来は複数の人間で行う、広告アイディアをひねり出すための手法ですが、
┃
┃ ご自分の《長所》や“商品”のセールスポイントを発見するための
┃
┃ 方法としてアレンジ、活用することができます。
┃
┃
┃
┃ 手順は、カンタンです。
┃
┃ 一つのテーマ(ここでは、ご自分や商品)について、
┃
┃ その長所やセールスポイントを、思いつくままにノートに書きとめる。
┃
┃ いいかげんはダメですが、自己規制せず、できる限り数量を求めて。
┃
┃
┃
┃ 複数の人たちで行う場合は、絶対に、他の人を批判してはいけません。
┃
┃ 他者の意見に賛同、便乗して、さらに考えを発展させることはOKです。
┃
┃
┃
┃ できるだけ、資料になるものを用意し、あんまりかしこまらないようにして、
┃
┃ たとえば「短気だって言われるけれど、それって、情熱的ってことだよね」
┃
┃ ぐらい、楽観的に行うのがいいのです。
┃
┃
┃
┃ テーマも「30代の主婦に対して」とか、「北国出身の人たちに対して」とか、
┃
┃ 可能な限り絞り込んでおいたほうがいいです。
┃
┃
┃
┃ 時間は、そんなに費やさないで、短時間に集中して行ってください。
┃
┃ 体験的には、一人でノートを相手にするのなら30分?1時間。
┃
┃ 複数で行うなら、その半分の15?30分ぐらいが適当です。
┃
┃
┃
┃ 結果は、できれば半日ぐらい時間をおいてから、
┃
┃ じっくりと整理・整頓してください。
┃
┃ この整理整頓作業で、より現実的に、客観的に、
┃
┃ テーマについてまとめていくわけです。
┃
┃
┃
┃ これが、ずっと説明してきた“考えるための素材”となり、
┃
┃ 商品開発や販売戦略、広告戦略の“核”となっていくわけです。
┃
┃
┃
┃ 何をアピールしたらいいのか、わからない。
┃
┃ いまのメッセージの仕方は本当によいのだろうか?
┃
┃
┃
┃ そんな方は一度、客観的に見直す意味で、
┃
┃ ブレインストーミング(精神の錯乱状態、という意味)を
┃
┃ 実施してみることをおすすめします。
┃
┃
┃
┃ 今回は、実例解説はお休みします。ご了承ください。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ 写真撮影・画像処理 ・・・・・・・・・・◇ 倉田 浩路 KURATA HARUMICHI
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ロ ケ ハ ン っ て 何 ?
┃
┃
┃ 今回は、倉田(兄)講師が撮影取材で不在のため、
┃
┃ ピンチヒッターで、私、風嶺が《ロケハン》についてお話します。
┃
┃
┃
┃ ロケーション・ハンティング--。
┃
┃ 本来は、撮影場所を探すこと。
┃
┃ もしくは、撮影場所をチェック(下見)することを意味していました。
┃
┃ もちろん、現在でも、それが正しいのですが、
┃
┃ 最近では、「それじゃあ、ロケハンに行ってきます!」なんて、
┃
┃ 若いスタッフが使っていることもしばしば。
┃
┃
┃
┃ 「えっ?今日は撮影本番じゃなかったっけ?」
┃
┃ 「そうですよ。ロケハンですよ」
┃
┃
┃
┃ なんて、有名大学を現役で入学卒業したような優秀な人材が口にする。
┃
┃ そうです。ロケハン=撮影取材と短絡的に、というか、
┃
┃ スタイリッシュに捉えている向きが少しあるようです。
┃
┃
┃
┃ 「ホームページに気の利いたビジュアルを掲載したいな」
┃
┃ と思ったとき、デジカメはとても手軽ですよね。
┃
┃ だから、外に出かけて、いろんなものをパシャパシャ撮ってしまう。
┃
┃ 「あっ、コレ、いいじゃん」なんて気軽に掲載してしまうと、
┃
┃ 実は大変なことになりかねないのです。
┃
┃
┃
┃ 察しのよい読者の皆さんなら、もう、おわかりですよね。
┃
┃
┃
┃ 具体的に所有者が特定できるものや著作物などは、
┃
┃ できる限り許認可を受けるようにしてください。
┃
┃ 特に、営利目的であったり、公共的な広報目的であっても
┃
┃ 露出規模が大きかったりする場合は、事前に担当窓口に
┃
┃ 確認しておいたほうが賢明です。
┃
┃
┃
┃ あるイメージを創造するために、特定メーカーの商品を撮影し、
┃
┃ 掲載する場合は、そのビジュアルが、その商品および企業イメージを
┃
┃ 損なわない限り、逆に宣伝効果となるので、不問となるのですが、
┃
┃ 人の解釈は千差万別ですので、この点も用心が必要です。
┃
┃
┃
┃ 「自分でお金を出して購入したものなんだからいいじゃない!」
┃
┃ といっても、どんなふうに使用してもよいとは限らないのです。
┃
┃
┃
┃ どうしても、ほしいビジュアルがある場合、
┃
┃ どうしても撮影したい場合は、次のような手順を踏むことをおすすめします。
┃
┃
┃
┃ 担当窓口(普通の住宅であれば、その家の、できれば世帯主か、
┃
┃ それに準じる方)に事前に連絡をとり、撮影許可を求める。
┃
┃ 企業やお役所、ミュージアムのようなところだと、
┃
┃ 撮影目的や掲載物等について記載した
┃
┃ 「申請書」の提出が必要な場合もあります。
┃
┃ また、その審査に数日を要するというところもあり、
┃
┃ 意外に面倒ではあるのです。
┃
┃ ではありますが、公式に許可されるのと、されないのとでは、
┃
┃ ひとたび問題が生じたときに大きな差がでます。
┃
┃ 場合によっては、損害賠償なんてこともありえないとはいえません。
┃
┃
┃
┃ 私もそのむかし、情報誌の撮影取材で、
┃
┃ 取材スポットをコーディネートしていたときに、
┃
┃ 大失敗を演じてしまったことがあるのです。
┃
┃
┃
┃ 私がある企業をインタビュー取材しているとき、
┃
┃ そのとき組んでいた、海千山千のベテランカメラマンが、
┃
┃ 「じゃ、オレは、先にほかのところを適当に撮影しておくから」と
┃
┃ 消えてしまったのです。
┃
┃ それは、表紙に使用する写真の候補のいくつかだったのですが、
┃
┃ 何を撮影したのか把握できず、カメラマンとディレクターに
┃
┃ セレクトを任せきりにしてしまったのです。
┃
┃
┃
┃ 発行日から間もなくしてディレクターが血相を変えているのが
┃
┃ わかる声で電話をかけてきました。
┃
┃ 「なんで、あの写真をカメラマンに撮らせたんだよ。あれは違法物件で、
┃
┃ 行政と歳晩沙汰になっているところなんだ。いま、クライアントに読者から
┃
┃ クレームの電話がいっぱい入ってきているって。とにかく謝罪に…」
┃
┃
┃
┃ 私は何のことだか皆目見当がつきませんでした。
┃
┃ 後日、話を聞くと、カメラマンは私が候補として挙げておいた場所ではなく、
┃
┃ 独断で自分がよいと思った風景を、その場で確認もなしに撮影していたそうで、
┃
┃ ディレクターには身の潔白を証明できたのですが、
┃
┃ クライアントにはそれでは済まされません。
┃
┃ 頭を下げに謝罪に行きました。
┃
┃
┃
┃ むかしかたぎのカメラマンには、そういった結果オーライ派が
┃
┃ 多かったのかどうかはわかりませんが、
┃
┃ 超年輩のベテランでもそうなのです。
┃
┃
┃
┃ 手間のかかる申請作業ですが、場合によっては、
┃
┃ それによって、普段なら決して立ち入ることのできないような
┃
┃ 場所に入れてもらえることもできます、
┃
┃
┃
┃ 大きく括ってしまえば、撮影のマナーとでもいうのでしょうか。
┃
┃ できる限り守って、素晴らしい絵づくりにカメラを活用してほしい。
┃
┃ と思います。
┃
┃
┃
┃ 今回はピンチヒッターでしたが、
┃
┃ 次回は予定通り倉田(兄)講師が再び登壇するはずです。
┃
┃
┃
┃ 皆さん、難題をメールで大量に送って困らせてあげましょう。
┃
┃ では、また機会があれば。風嶺でした。
┗
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ★ プランニング ・・・・・・・・・・・・・・◇ 西 佳宏 NISHI YOSHIHIRO
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━『 売 る た め の ス キ ル 』を 磨 こ う!
┃
┃
┃ 大好きな片思いの人を口説くとき、あなたはどうしますか?
┃
┃
┃
┃ ただ黙って見つめているだけですか?
┃
┃ 恋しい人と一緒になるために努力しますか?
┃
┃ そして、あなたは「恋」と「愛」の違いがわかりますか?
┃
┃
┃
┃ 片思いを両思いにしようと、誉めまくったり、なだめたり、
┃
┃ 思うようにならないと、脅したりまでする。
┃
┃ これらは、すべて、“自分自身が満足したい”から起こす行動です。
┃
┃ そこには、片思いしている“相手の気持ちを汲む”という発想がありません。
┃
┃
┃
┃ これでは、相手は振り向いてくれないでしょうし、
┃
┃ 好きになってくれるわけがありません。
┃
┃
┃
┃ 「恋」は、“自分の気持ち”に忠実に行動すること。
┃
┃ 「愛」は、大好きな“相手の気持ち”になって行動すること。
┃
┃
┃
┃ 《自分》という人間を、どのように活かすか、根本から違っているのです。
┃
┃
┃
┃ ホームページを、大好きな人と置き換えると、
┃
┃ あなたのすべきことが見えてくるはずです。
┃
┃
┃
┃ 自分の思いだけで作らずに、来訪者の気持ちを考えて作る。
┃
┃
┃
┃ アフィリエイトひとつを取ってみても、
┃
┃ 「売るためのノウハウ」を、どこかから探してきて盛り込むより、
┃
┃ “情報を収集しにきた”来訪者の欲しい情報が、
┃
┃ 盛り込めているかどうかが、大事です。
┃
┃
┃
┃ 愛する人が、今、何を欲しがっているのか?
┃
┃ 喜んでもらうためには、リサーチが必要ですね。
┃
┃ そして、目星を付けたプレゼントを用意して、
┃
┃ さりげなく傍らに置くことでしょう。
┃
┃
┃
┃ 来訪者は“情報収集にくる”と言いましたが、
┃
┃ 目的に適った情報があれば、対価を支払う用意があるということです。
┃
┃ それが商品であれば“購入”という行動になります。
┃
┃
┃
┃ いかに気持ち良く、情報を読んだり見てもらえるか、
┃
┃ “情報の整理整頓”が「デザイン」です。
┃
┃
┃
┃ 「売るためのスキル」とは、
┃
┃ 来訪者の立場になって、どうすれば“共感”が引き出せるか、
┃
┃ を考えることです。
┃
┃
┃
┃ 人に教えてもらったテクニックではなく、
┃
┃ 自分で試行錯誤しながら身に付ける「オリジナルノウハウ」のことです。
┃
┃
┃
┃ ここで2つの情報を見てください。
┃
┃ http://simple.sub.jp/sam_2.html
┃
┃ http://simple.sub.jp/sam_1.html
┃
┃
┃
┃ 今のあなたの心の琴線に触れるコメントはありましたか?
┃
┃ もし、あったとしたら、わたしの試みは効果があったということですね。
┃
┃
┃
┃ 「売るためのスキル」は試行錯誤から修得するべきものです。
┃
┃ 試し続ける気持ちを持ち続け、
┃
┃ その結果を経験として蓄積すること、
┃
┃ それが「売るためのスキル」を磨くことなんです。
┃
┃
┃
┃ ※やる気とノウハウ修得の早道
┃
┃ http://simple.sub.jp
┗
☆ インフォメーション-------------------------------------------- 編集後記
今号も最後までお読みいただきありがとうございます。
これまで、自ら好んで業界に飛び込んできた後輩たちに指導してきた
私たちが、失礼な言い方かもしれませんが、ことデザインに関しては
モチベーションの低い素人の方々にどうアドバイスすればよいのか。
試行錯誤してきた1ヶ月でした。
でも、皆さん、積極的にご要望やご質問をお寄せいただき、
その文面から、デザインやコピー作成にモチベーションが低いどころか、
「初心」というふた文字を逆に私たちに思い起こさせていただきました。
デザインやコピーは“生もの”です。
なぜなら、それは、新鮮な“いま”という情報を伝えるものだから、です。
その意味で、常に「初心」を心掛けることは、とても大切なことなのです。
このメルマガを通じて、「初心」をいつまでも維持できるといいな、と、
思っています。
皆さんからのメールや質問も、引き続き受け付けています。
ぜひ「こんなことを教えてほしい」「私のサイトを見てアドバイスを」等の
ご要望やご意見を遠慮なくどうぞ。
送信先は、編集責任者である“風嶺”へ。
▽継続購読していただくための塾生サービスの紹介!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
├─その1:サイトと連動したビジュアルな展開により、 ┃
┃ ┃
┃ イラストや図を活用して、 ┃
┃ ┃
┃ 見て理解できるわかりやすさを追求! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その2:塾生(購読者)専用のフォーラム(掲示板)を開設! ┃
┃ ┃
┃ わからない部分や聞きたいことを、ピンポイントに講師に ┃
┃ ┃
┃ 尋ねることができます!! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その3:フォーラムを通しての塾生間交流や情報収集もOK! ┃
┃ ┃
┃ 人脈づくりにも有効に活用していただけます。 ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その4:仲間の存在により、モチベーションの維持だって図れます! ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その5:ホームページやインターネット関連にとどまらず、 ┃
┃ ┃
┃ グラフィックデザイン、広告活動、SP戦略など、 ┃
┃ ┃
┃ 広告・広報に関する幅広い専門知識の吸収も可能です。 ┃
┃ ┃
┃ ┃
├─その6:本格的にしたいけど自分では・・・という方には、 ┃
┃ ┃
┃ 実際に講師スタッフがお仕事の依頼を受けることも可能。 ┃
┃ ┃
┃ 塾生割引有り? ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆
◇ お待たせしました!『塾生フォーラム』の開設のお知らせ、です
◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
長らくお待たせいたしましたが、
インタラクティブなコミュニケーションで、さらに「売れるページ」に
加速接近できる『塾生フォーラム』を12月上旬からスタートさせます。
このフォーラムは、当塾の西佳宏講師が発行している2つの有料e-Book
「来訪者を逃さないホームページデザインのコツ!」
「『まぐまぐ』でメルマガ初心者がデビューするためのノウハウパック!」
の購読者専用フォーラムとして先行開設されているものです。
原則として《有料購読者さま限定》の開放となり、
入室に際しては、「ID」「パスワード」が必要です。
「ID」「パスワード」の発行方法、有効期限などについては、
連絡用メルマガにてお伝えいたします。
━o(^-^)○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「釘づけサイトのデザイン塾」(原則として毎週金曜発行)
企画・発行:クー・アートメディア http://www.ku-am.co.jp/
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-4-1-103
編集者・お問合せ:風嶺 瞭 kw800096@fsinet.or.jp
(C) 2005 Ku: Art Media Inc. All rights reserved.
掲載の記事の無断転載を禁じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |